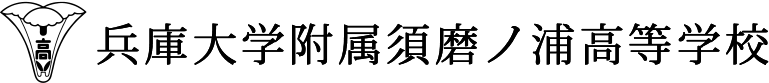【1/29神戸新聞掲載記事より】
震災当時の教諭ら3人 須磨ノ浦女子高、あの日を振り返る 「学校つぶれている」がくぜん
1995年の阪神・淡路大震災で神戸市須磨区の校舎が全半壊し、大半の教室が使用不能となった須磨ノ浦女子高校 (現兵庫大付属須磨/浦高)。生徒と教員は再建までの約2年間、同じく学校法人陸学園が運営する兵庫大(加古川市平岡町新在家)敷地内の仮設校舎で過ごした。震災の記憶や学び舎の移転、加古川市での学校生活について、当時若手教員だった田尻善紀教頭、池田紀子教諭、岡本菜穂子教諭に語ってもらった。(聞き手・田中朋也)
―震災で校舎1棟が全壊、2棟が半壊した。半壊でも4階の廊下から1階が見えるほどの穴が開くなど、70教室のうち 65教室が使えない状況。最初に駆け付けたのは池田教諭だった。
池田 課題考査の日で、加古川市の自宅をいつもより早く出たところ大きな揺れがあり、停電。車で学校に向かったが、 加古川でも信号が消えていた。午前7時半ごろ学校に到着。校舎の被害の大きさにがくぜんとした。その後、半壊だった校舎の職員室から教職員に連絡を取った。
田尻 神戸市内の自宅マンションで家族も無事だった。同僚から「学校がつぶれている」と連絡があり、ミニバイクで学校へ向かったが、近づくにつれ被害が大きくなり、空は長田区の火災の煙で覆われていた。
岡本 教員が集まると手分けして生徒の安否を確認した。私は自転車で近隣の生徒の家を回った。(9日後に)生徒全員の無事を確認できた時は、教員みんなが胸をなで下ろした。
池田 避難している家庭もあったので、張り紙をする先生もいた。
―2月2日、兵庫大の敷地に仮設校舎を建て、再建まで移転することを決定。早々に机や椅子の搬出など準備が始まった。4月5日に仮設校舎が完成し、加古川での学校生活が始まった。
岡本 当時の学校周辺は生徒たちが安心して学べるような状況ではなかった。私自身、仮設校舎に来た時はほっとした。
池田 震災前は指導にすんなり従わなかった子が、つぶれた校舎を見て「学校来られへん」と泣いた。学校への思いが強いことを実感した。加古川での初登校は、みんなうれしそうだった。学校に集まれることで、安心したのではないか。
田尻 仮設校舎ではとにかく生徒が和やかだったという記憶がある。仮設の職員室前によく生徒が集まっていた。生徒と教員との距離感が近かった。
一96年12月、須磨の新校舎が完成し、 2学期の終業式を実施。加古川での学校生活が終わった。
池田 震災で心に傷を負った生徒もいただろうし、行事を十分に行えない不自由さもあった。それでも「みんな一緒やから」という感覚があり、生徒が不安を打ち明けてくれることも多かった。受け持ったクラスでは震災を教訓にして「今の生活が当たり前ではないよ」と伝える。
震災講話 毎年続ける 兵庫大附須磨ノ浦高
「言葉ではなかなか伝えられない被害だった」。今年1月17日、兵庫大付属須磨ノ浦高校の小笠原仁副校長(62) は生徒約650人を前に語った。同校は毎年この時期、震災を語り継ぐ講話を行う。生徒たちに当時の新聞記事などを見せ、備えの大切さを訴える。
写真や映像を交えた説明の後「視覚では分かりにくいが」と付け加えた。
実際の避難所では、生活臭や消毒液のにおいが混ざったような空気が充満していたこと、盗みや性被害の恐れがあること、震災時の火災は停電後に再度通電した時に出火する「通電火災」が一因であること・・・。
講演後、生徒会長の覚咲良さん(17) は「準備を重ねることが大切。下の世代にも伝えていく」。3年の成瀬梨菜さん(18)は「今後、大きな地震が来ることも想定されている。知る範囲でしか話せないけど、これまでのこと、これからのこと、しっかり伝えていきたい」。(田中朋也)
バレー部主将・宮崎さとみさん(当時2年)春高中止「何を目標にすれば」
震災当時、須磨ノ浦女子高校のパレーボール部主将で2年の宮崎さとみさん は卒業までを加古川市内の仮設校舎で過ごした。部員一丸で挑むはずだった 1995年の全日本高校選手権(春高バレー) の予選は中止に。落胆する宮崎さんを勇気づけたのは仮設校舎で再会した級友たちの存在だった。
宮崎さんは神戸市垂水区の寮で被災。 5人ほどが寝起きする部屋の2段ベッドの上で揺れを経験した。寮は大きな被害を受け、向かいの中学校に避難した。
しかし、プールの水でトイレを流すなどライフラインが機能しない状態。部員約20人は数日後、加古川市の合宿所へ移った。寮から車で1時間。それだけで電気やガス、水道が使える環境の差に驚いた。練習再開後に春高バレー予選中止の報が入る。「何を目標に練習すれば・・・」 とやるせない気持ちが募った。
同年春、仮設校舎での新生活が始まった。家族や先生の支えで食事や衣服には困らなかった。一時はどうなるのかと思った高校生活だったが、級友との再会に安堵した。「みんな生きている」。夏のインターハイへ向けて気持ちがふつふつと沸き立った。県大会を勝ち上がり、インターハイ出場がかなった。
2011年秋、東日本大震災の被災地を訪れる機会があった。惨状を前に自分が恵まれていたこと、復興へ向かう人の強さを実感した。母校を思い「私たちの先生は頑張ってくれたんだ」。今はそう思う。(田中朋也)
【関連するページ】
・2025.01.17 阪神・淡路大震災から30年 1・17
・2025.01.17 震災から30年・・・「御正忌報恩講並びに阪神淡路大震災追悼礼拝」開催
・2025.01.17 「1.17いのちを考える研修会」作文朗読